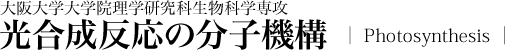研究内容
1.光合成反応中心のエネルギー変換機構
1-1. はじめに
(1) 概略
一兆分の一秒の光化学反応を追いかけて
光化学反応は、ある特殊環境におかれたクロロフィル色素の二量体(P)が光エネルギーによって励起され(P*)、一次電子受容体(A)との間で初期電荷分離(P+A-)を引き起こすことによりはじまります。生じた高いエネルギー状態の電子は、バケツリレーのごとく次々といろんな電子伝達成分(B, C, ・・・)に渡されていき、最終的には同化反応等に必要な還元力(NADPH)が作り出されます。それぞれの電子伝達反応に要する時間はきわめて短く、初期電荷分離には約一兆分の一秒(~3ピコ秒)、全体の反応でも約一万分の一秒(~100マイクロ秒)ぐらいで終了してしまいます。私たちはこのような反応を、孤軍奮闘しながら日夜追っかけているのです。
![]()
ナノスケールのエネルギー変換装置
植物の光合成の場は、細胞内小器官の一つである葉緑体です。葉緑体を電子顕微鏡で覗いてみれば、座布団のようなものが折り重なった膜系(チラコイド膜)が発達していることがわかります。先ほど説明した高速の反応は、このチラコイド膜内に埋まっている光化学反応中心とよばれる色素タンパク質複合体が担ってるのです。近年の分子生物学や構造生物学のすばらしい研究成果によって、光エネルギーの変換過程を分子のレベル(ナノスケール)で理解することが可能となってきました。
光化学反応中心には系II型(キノン型:タイプ2ともいう)と系I型(Fe-S 型:タイプ1ともいう)の 2 種類が存在します。高等植物やらん藻では、これらはb6 / f 複合体を介して直列につながっていて、水分子から電子をひきぬくことができる強い酸化力と、NADP+ を還元する強い還元力とを、同時に生み出すことが可能な仕組みになっています。一方、光合成細菌はどちらか1種類のみの反応中心しかもちません。紅色細菌の反応中心は比較的安定で取り扱いが容易であったため、膜蛋白質複合体として、世界ではじめてX線結晶構造解析が成功したことは有名です(1988年ノーベル化学賞)。さらに1996年にはシアノバクテリア(ラン色細菌:以前はらん藻とも呼ばれていた)光化学系Iの立体構造が分解能4Åで、1998年には植物光化学系IIが分解能8Åで解かれました(残念ながら低分解能であるため、個々のアミノ酸残基までは同定されていません)。そして2001年、シアノバクテリア光化学系IおよびIIの立体構造が高分解能(それぞれ2.5Åと3.4Å)で報告されるに至りました。今後は分光データーの構造的側面からの解釈へと大きく進展していくものと期待されます。

植物の光合成電子伝達系
すでに説明したように、植物葉緑体(およびシアノバクテリア)のチラコイド膜には、2種類の光化学系が存在し、チトクロムb6/fを介して直列につながる電子伝達経路を構成しています(これを直鎖状電子伝達系、もしくは非循環的電子伝系と呼びます。非循環的電子伝達系と呼ぶ理由は、ここでは詳しくは触れませんが、光化学系1からキノンプールもしくはNADHデヒドロゲナーゼに電子が流れるような循環的回路の存在があるからです)。光化学系の概念は、1940-60年代にかけて確立されましたが、なかでもエマーソン効果の発見はHillとBendallによる斬新で革新的なZスキーム(非循環的電子伝系)の提唱へとつながっています。その後、幾多の試練を経て、光合成の教科書には必ず載っているスキームが出来上がりました(上図参照)。

植物葉緑体の光合成電子伝達系(出展:ヴォート生化学(東京化学同人)から)
紅色細菌の電子伝達系
紅色細菌はタイプ2(キノン型)の反応中心を一つしかもたない光合成細菌で、チトクロムbc1複合体との循環的な電子伝達経路を構成しています。QBサイトで2電子を受けったキノンは、サイトプラズム側から取り込んだ2個のプロトン(H+)によりキノール(QH2)に還元されます。このキノールはチトクロムbc1により酸化され、放出された2電子のうち1個はチトクロムc2、もう1個はヘムbへと流れます(これはQサイクルモデルとして説明されていて、化学浸透圧説でノーベル化学賞をもらったMichellが提唱したモデルです。このモデルの正当性は、チトクロムbc1複合体およびチトクロムb6f複合体の立体構造解析から支持されています)。この際、2個のプロトンもペリプラズム側に放出され、これが膜を介したプロトン濃度勾配形成の仕組みとなっているわけです。生合成系に必要な還元力(NADPHや還元型Fdなど)は、形成されたプロトン濃度勾配を利用してつくられるといわれていますが、実はそのメカニズムはまだ詳細には解明されていません。

紅色細菌の酸素非発生型光合成電子伝達系(出展:Brock Biology of Microorganisms 10th)
緑色イオウ細菌の電子伝達系
緑色イオウ細菌はタイプ1(Fe-S 型)の反応中心を一つしかもたない絶対嫌気性の光合成細菌で、その電子伝達系は未解明な副次的経路の存在が示唆されていますが、基本的には直線的な「非循環型」と考えてよいでしょう。電子源である硫化物等の還元イオウ化合物を出発点として、最終的にタイプ1反応中心により生体還元力NADPHを生成しています。イオウ酸化経路は非常に複雑で、その全貌はまだ明らかとなっていません。イオウは-2から+6までの価数をもつ元素であり、無機化学としても興味深い対象ですが、イオウ代謝系の中間体を同定するには特殊な分析方法が必要なこともあり、世界的にもあまり研究は進んでいません。多成分酵素系を構成するSox系の各酵素の機能解析については、化学合成細菌の一種であるParacoccusが一番よく分かっています。近年はイオウ酸化細菌のゲノム解析が大きく進展し、比較ゲノムの観点から緑色イオウ細菌のイオウ代謝系の研究を進めようとする動きがあります。また、もう一つ、私たちが注目していることは、緑色イオウ細菌のゲノム上にはNADH oxidoreductaseをコードする遺伝子が1セット存在していることです。この遺伝子セットは、ちょうど植物の葉緑体チラコイド膜のNDHと同じであり、おそらくサイクリック経路が存在しているのではないかと推測しています。緑色イオウ細菌はチオ硫酸のみで生育することができますので、何らかの経路で(プロトンの電気化学ポテンシャルを利用した)ATP合成を行う必要があるからです。

緑色イオウ細菌の酸素非発生型光合成電子伝達系(Tsukatani et al. 2010)
光合成反応中心の構造
2001年になってシアノバクテリアの光化学系I(PS I)およびII(PS II)の立体構造が高分解能で報告されました(光化学系IIについては2010年、水分解酵素を含め、さらに高分解能の構造が報告されています)。紅色細菌の反応中心は比較的安定で取り扱いが容易であったため、膜蛋白質複合体として、世界ではじめてX線結晶構造解析が成功したことは有名です(1988年ノーベル化学賞)。紅色細菌の反応中心は植物葉緑体およびシアノバクテリアの光化学系II反応中心の祖先型であることが分かっています(紅色細菌の反応中心から光化学系II反応中心が進化してきました)。一方、緑色硫黄細菌の反応中心の立体構造は未だに不明ですが、緑色硫黄細菌の反応中心から光化学系I反応中心が進化してきたと考えられています。これまで立体構造の明らかと成った紅色細菌反応中心、光化学系II反応中心、光化学系I反応中心のコアタンパクはすべて、2つの相同なポリペプチドから構成されるヘテロダイマーです。構造上、ほぼ対称的な2つの反応経路が形成されていますが、その非対称的なタンパク環境により、一方の経路のみを優先的に使って電子移動反応は行なわれています。紅色細菌反応中心と光化学系II反応中心では左の電子移動経路のみが機能し、光化学系I反応中心では左が約60%、右が約40%ほどの確率で電子が移動反応が起こっています。実は緑色イオウ細菌(およびヘリオバクテリア:ここでは示していない)反応中心のコアタンパクは一種類のポリペプチドから構成されていて、ホモダイマー構造をとっています。対称的な蛋白環境を形成するホモダイマー構造であるなら、電子伝達成分の配置やその反応経路等、どのようになっているのでしょうか?長い進化の過程で、なぜ緑色イオウ細菌だけにはヘテロ化が生じなかったのでしょうか?私たちは「ホモダイマー型光合成反応中心の反応特性と電子移動経路」に興味をもち、研究を進めています。

光合成反応中心の構造と電子移動経路の比較
(2) 何を知りたいのか
ホモダイマー型反応中心の謎にせまる
緑色イオウ細菌のもつ光化学反応中心は、研究の歴史としては古いものの(1950年代に始まる)、エネルギー変換に関わる電子伝達系の知見についてはごく最近までほとんど手つかずの状況でした。1990年代に入り、ようやくタンパクレベルでの研究が本格的にスタートし始めました。その理由は、今まで研究材料の調製が難しかったのですが、嫌気的手法(無酸素の状態で調製を行うことを意味します)を導入することによって非常に安定な標品を得ることができるようになったからです。もちろん、私たちもこの研究に参画することになりました。
ここで不思議なことが一つあります。緑色イオウ細菌(およびヘリオバクテリア)反応中心のコアタンパクは一種類のポリペプチドから構成されていて、ホモダイマー構造をとっているものと推測されています。実はこのことが、電子伝達経路に重要な問題をなげかけるに至っているのです。他の反応中心(紅色細菌反応中心、植物やシアノバクテリアの光化学系 I と II )のコアタンパクはすべて、2つの相同なポリペプチドから構成されるヘテロダイマーです。構造上、ほぼ対称的な2つの反応経路が形成されているのですが、非対称的なタンパク環境により、一方の経路のみを優先的に使って電子伝達反応は行なわれています。もし緑色イオウ細菌反応中心が、対称的な蛋白環境を形成するホモダイマー構造をとっているとするならば、電子伝達成分の配置やその反応経路等、いったいどのようになっているのでしょうか?長い進化の過程で、なぜ緑色イオウ細菌だけにはヘテロ化が生じなかったのでしょうか。光合成電子伝達反応において、まだ誰も知らない重要な謎がここにはかくされているようです。